Progmat、日本版トークン化株式の検討開始


ブロックチェーン基盤のインフラを提供するProgmat(プログマ)は4日、日本版トークン化株式(ST)の検討を開始すると発表した。
野村、三菱UFJ信託、SBIをはじめとする大手金融機関24組織と共同検討する。
同社は「トークン化法・株式STワーキング・グループ」を設置し、株式をブロックチェーン上で取引可能にする仕組みを検討する。Progmatは三菱UFJ信託銀行の子会社で、ブロックチェーン技術を活用した金融インフラの構築を手がけるスタートアップ企業である。
現在の日本株市場では、100株単位でしか原則売買できない。証券取引所では少額取引がしづらく、株式保有の中心は外国法人等となっている。本来、その受け皿として期待される国内の個人投資家だが、1985年頃からほぼ横ばいで17%近傍に留まっており、「少額投資」の環境整備が他国比で遅れているのが実情。
一方で、個人株主数自体は大きく伸びている。これは、東証による「望ましい投資単位(50万円未満)」への引き下げ促進策により、上場企業の株式分割が進み、着実に効果が出ていることを示している。
特に注目すべきは、個人株主のうち最も伸び率が高いのが「単元未満株のみ株主」である点。単元未満株とは100株未満の株式を指し、原則として譲渡性がなく(証券取引所で売買ができない)、議決権も排除されている。
2023年度は、総株主数(延べ)約8,785万人のうち、13.4%にあたる約1,175万人(延べ)が「単元未満株のみ株主」となっている。
少額投資の環境が整備されることで、個人投資家、すなわち売買のタイミングや方向が異なる様々な投資家が参加しやすくなる。これにより、過度な株価変動の抑制や市場の流動性向上、上場会社の株主構成の多様化に寄与することが期待される。
今回の構想では、預託証券(DR)方式を採用し、信託の仕組みで株式を小口化することで、1円単位からの購入を実現する。他にも複数の証券会社間での取引や24時間取引ができる見込み。
配当金は保有量に応じて分配され、議決権も持株会のように意思表示に基づいて代表者が行使する形を想定している。海外で展開されている株式連動トークンの多くは議決権を持たないため、これは日本版の大きな差別化ポイントとなる。
発行体企業にとっては、従来の総株主通知(年2回~4回)よりも鮮度高く権利者をリアルタイムで把握でき、実効性の高いマーケティングによる「ファン株主」化の促進が可能になる。政策投資株縮小の流れの中で、新たな安定株主層を確保する手段としても注目される。
流通チャネルは大阪デジタルエクスチェンジ(ODX)などの私設取引システム(PTS)を活用する想定。税制面では、既存の不動産STと同様に申告分離課税が適用可能で、特定口座も利用できる見込み。
ワーキング・グループは2025年11月にキックオフし、2026年3月に報告書と「トークン化法」の立法素案を公表する。同法は株式だけでなく、投資信託や地方債など、あらゆる有価証券を対象とした包括的な法整備を目指す。2026年春から実際の商品開発を始める予定だ。
海外ではBacked Financeが米国株60銘柄超を24時間365日取引可能にし、Ondo Financeが100銘柄超を提供している。ギャラクシー・デジタルは9月、ナスダック上場企業として初めて株式そのものをソラナ上でトークン化した。いずれも暗号資産取引所やDEX(分散型取引所)で展開を広げている。
ナスダックは米国証券取引委員会(SEC)に、トークン化株式を既存株式と同じ取引板で売買可能にする規則改正案を提出済みだ。決済大手DTCが従来の株式と同様に決済を担う仕組みで、米国での本格的な制度化に向けた動きが加速している。
関連: ナスダック、トークン化株式の取引承認を申請一年後に米国初の実現目指す
関連: プログマとは?デジタル証券・ステーブルコインなど対応のブロックチェーン基盤を徹底解説
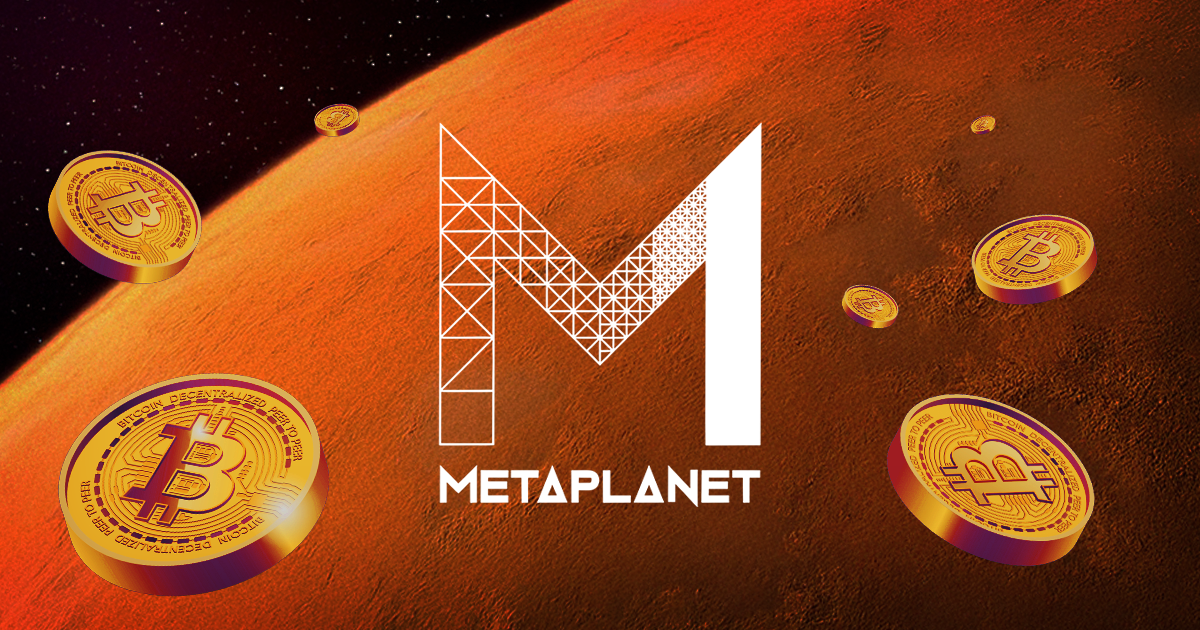
メタプラネット、保有するビットコイン担保に1億ドル調達
メタプラネットが保有ビットコインを担保に1億ドル(約153億円)を借入。資金はビットコインの追加取得やインカム事業に充当。同社は30,823BTCを保有しており、2027年末までに21万BTC取得を目...

リップル社のステーブルコイン「RLUSD」 流通額10億ドル突破
リップル社の米ドル連動ステーブルコイン「RLUSD」が時価総額10億ドルを突破。非営利団体や米Bitnomial取引所で採用が進み、実需型ステーブルコインとして存在感を高めている。...
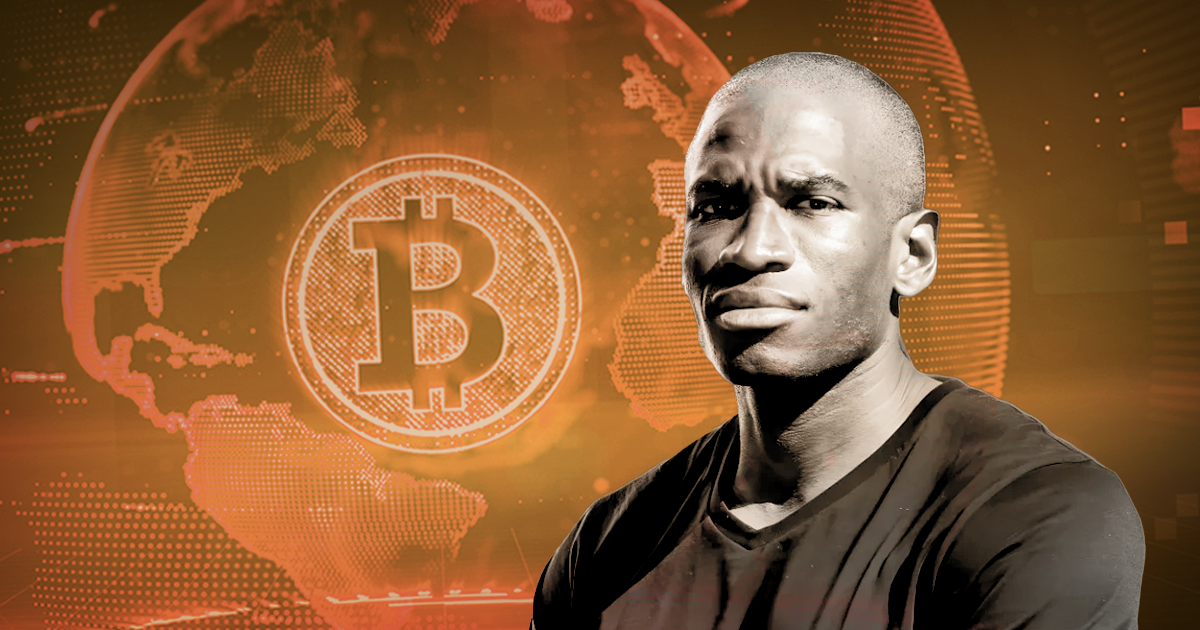
アーサー・ヘイズ、FRBの実質QEでビットコイン強気相場再開と予測
ビットメックス共同創業者アーサー・ヘイズ氏は、FRBが常設レポファシリティを通じた実質的な量的緩和(QE)により、ビットコイン強気相場が再開すると分析した。米国債発行増加でSRF残高が拡大しドル供給が...

