米国Web3規制の最新動向|CLARITY・GENIUS法案と企業参入の影響を徹底解説


2024年の米国の大統領選で「米国を暗号資産(仮想通貨)の中心地にする」と公約したドナルド・トランプ氏は、就任後に実際の制度整備に着手しました。かつて国家レベルのWeb3制度がなかった米国では、現在、ルール整備が急速に進められています。
狙いとしては、ブロックチェーン技術を通じて米国が国際的リードを握ることや、米ドル基軸体制の維持に向けたステーブルコインの普及促進が挙げられます。
制度整備の進展により、参入を控えていた企業の動きも活発化。トランプ政権は規制明確化だけでなく、緩和や業界支援策も進めており、Web3企業の米国市場参入を後押ししています。
本記事では、米国のWeb3制度整備と業界動向を整理し、日本の制度整備にも言及します。投資家や業界関係者が全体像を把握する手助けとなれば幸いです。
この章では、米国で注目される2つの主要法案を軸に、Web3制度整備の全体像とその影響をわかりやすく整理します。特に、制度の明確化が金融・決済・投資の分野でどのような企業行動を促すのかを中心に解説します。
これらの法案はいずれも、仮想通貨やトークンに関する 規制の明確化 と、 企業によるWeb3参入の円滑化 を目指すものです。法的な不確実性が解消されれば、企業はより安心して新規事業に取り組むことができ、業界全体の活性化が期待されます。
とくに以下の分野では、実際のビジネス展開が促進されると見られています。
一方で、マネーロンダリング対策(AML)や消費者保護、コンプライアンスの遵守も求められますが、制度とイノベーションのバランスを図ることで、持続的な成長につながると期待されています。
こうした制度整備を背景に、実際に多くの大手企業がWeb3事業に本格参入しつつあります( 第2章へ )。
CLARITY法案(Digital Asset Market Clarity Act of 2025)は、仮想通貨が「証券」か「商品」かの分類基準を明確に定めることを目的とした法案です。SEC(証券取引委員会)とCFTC(商品先物取引委員会)との間で曖昧だった管轄の整理が進み、プロジェクト側が遵守すべきルールが明確になります。
2025年7月25日時点では法案が下院で可決されて、上院での審議に移行しています。
CLARITY法案は、SECとCFTCの権限を明確にし、仮想通貨の大部分を有価証券の範疇から除外する内容を盛り込んでいます。また、デジタル資産企業には顧客への情報開示義務や顧客資金の分別管理を求めています。
他には、非管理型仮想通貨プラットフォームと開発者が、送金事業者や無免許送金サービス事業者として扱われないことを明確にする条項が追加され、これによりDeFi(分散型金融)開発者の法的リスクが軽減される見通しです。
GENIUS法案(Blockchain Regulatory Clarity Act of 2025)は、ステーブルコインの発行者・流通業者へのライセンス設計、カストディ(保管)業務の適正化、税制整備などを含む包括的な法案です。
この法案は、すでにトランプ大統領の署名まで進み、正式に法制化されており、Web3のインフラ整備と、金融機関の本格参入の制度的な基盤が築かれると期待されています。
GENIUS法は、発行体に認可制を導入することや認可を受けた決済用ステーブルコインは有価証券ではないことなどを定め、裏付け資産に米ドルや米ドル同様の流動性の高い資産を保有することを義務付けています。
注目を集めている点の1つが「域外適用」の概念が採用されていることです。これにより世界最大のステーブルコイン発行企業のテザーなど、米国外に拠点を置きながら米国人向けにサービスを提供する企業は、所在地に関わらず米国の規制に従う必要が生じます。
また、規制対象外として以下の項目などが挙げられており、DeFi領域への適用が除外されることも明確化されています。
政府が民間のステーブルコインを推進しようとする背景には、ドルの覇権強化以外にも、米国債の需要増加への期待があります
まず、ステーブルコインは米ドルに連動しているため、世界中で利用されることで米ドルの需要を高め、グローバルな金融システムにおける覇権強化につなげる狙いです。この狙いは、BRICSプラスなど、米国の伝統的な金融システムからの離脱を目指す国や地域の存在が念頭にあるとみられます。
また、米国債の需要が増える理由は、ステーブルコイン発行企業が裏付け資産を、国債を含む流動性の高い資産で運用するためです。結果的に、ステーブルコインの普及拡大が金利の低下につながり、国の財政を支えることを政府は期待しています。
米国では他にも、Web3と直接は関係はありませんが、「CBDC監視国家反対法案(Anti-CBDC Surveillance State Act)」の審議も継続中です。この法案は、連邦準備制度(FRB)が個人に対して直接CBDC(中央銀行デジタル通貨)を発行することや、CBDCを金融政策のツールとして使用することを禁止することなどを定めています。
また、少額免税措置を含めた仮想通貨税制改正法案もこれから審議されていく予定です。
この章では、Web3分野に参入する具体的な企業の動向を以下の分野別に解説します。
米メガバンクのバンク・オブ・アメリカ(バンカメ)のブライアン・モイニハンCEOが、ステーブルコインが合法化されれば「バンク・オブ・アメリカ コイン」として事業に参入する意向を表明しています。
モイニハン氏は「完全にドル裏付けされたステーブルコインが登場することは明らかです。これは小切手アクセス付きのマネーマーケットファンドや銀行口座と本質的に変わりません」と述べています。
JPモルガン・チェース
JPモルガン・チェースについて、取引・資産管理顧客に対して仮想通貨関連資産を融資の担保として利用できるサービスを開始する予定であることや、イーサリアムのL2チェーン「Base」上で預金トークン「JPMD」を発行する計画があることが報じられています。
これらもトランプ政権の規制緩和を見据えた動きとみられ、顧客の利便性向上やサービス拡充、速くて安価な取引サービスの提供を目指しています。
また、ジェイミー・ダイモンCEOがステーブルコイン事業の参入は避けられないと表明しています。
ゴールドマン・サックスとBNYメロン
ゴールドマン・サックスとBNYメロンが、ブロックチェーン技術でマネー・マーケット・ファンド(MMF)をトークン化する取り組みを共同で開始することを発表しました。
この取り組みは、既存のMMFの実用性や移転可能性を強化することへの重要なステップであるとし、機関投資家の進化する需要に応えていくと両社は説明しています。
企業連合
他にも、JPモルガン・チェース、バンカメ、シティグループ、ウェルズ・ファーゴらが共同でステーブルコインの発行を検討していることが報じられています。
この動きの背景には、決済のコスト低下や効率化向上などの目的に加え、IT企業や小売企業に預金や取引を奪われないようにする狙いがあるとの指摘があります。
アマゾン
Eコマース大手アマゾンは、独自ステーブルコインの発行を検討していることが報じられています。
ステーブルコインを決済に導入すれば、従来の決済システムを迂回して手数料削減が可能。カード決済時の手数料の高さや決済完了までの遅延の問題も解決され、特に海外サプライヤーとの取引で効果が期待されています。
メタ
マーク・ザッカーバーグ氏が率いるメタは、複数の仮想通貨企業とステーブルコインを活用した国際送金サービス実現の可能性を模索していることが報じられました。
報道によると、特にインスタグラム上でのクリエイターへの少額報酬支払いにおけるコスト削減に焦点を当てているようです。
アップル・X・Airbnb・グーグル
アップル・X・Airbnb・グーグルの4社が、複数の仮想通貨企業とステーブルコイン統合について初期協議を行っていることが報じられました。
各社は取引手数料削減と国際送金最適化を目的としてドル連動型デジタルトークンの採用を検討しています。
ファイサーブ
米決済大手ファイサーブは、独自ステーブルコイン「FIUSD」を含むデジタル資産プラットフォームの開始を発表。独自ステーブルコインを持つ決済大手PayPalと組む計画もあり、カードネットワークとの提携に向けた交渉も進めていると説明しました。
狙いは、ステーブルコイン決済の発展、ブロックチェーン金融サービスの民主化の推進、従来の決済システムにおける摩擦の削減、銀行の資本負担軽減です。
テザー
テザーのパオロ・アルドイーノCEOは、米国市場再参入戦略が「順調に進行中」と明かしています。新戦略は米国の機関投資家市場に焦点を当て、決済や銀行間決済、取引向けの効率的なステーブルコインを提供する計画です。
なお、テザーを巡っては、GENIUS法の施行によってUSDTが米国から実質的に締め出される可能性が指摘されています。
トランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ
トランプ氏やその家族に関連する企業も、Web3参入に積極的です。例えば、「Truth Social」を運営するトランプ・メディア・アンド・テクノロジー・グループ(TMTG)は、フィンテックブランド「Truth.Fi」を立ち上げました。
同社は、複数の仮想通貨ETFの申請を行っており、サービスの拡充や収益の増加を計画しています。
ステート・ストリートとシティグループ
ステート・ストリートとシティグループは、仮想通貨カストディ事業への参入を計画していることが報道で明らかになりました。
銀行らによるカストディ事業参入を実質的に阻んできたルールをSECが撤回したことで、大手金融機関が新事業を開始して新規顧客の獲得や収益の増加につなげようと動き出しているようです。
続いて本節では、上記以外の世界における有名企業のWeb3への参入事例や参入検討事例を整理します。
欧州で仮想通貨規制法「MiCA法」が制定されたり、米国で国家レベルのWeb3制度整備が行われたりして世界でルール作りが進んでいますが、日本も同様です。
日本は世界に先駆けて仮想通貨の規制整備を開始しました。いち早く仮想通貨交換業者に登録制を導入し、決済ステーブルコインのルールもすでに制定しています。
一方で、仮想通貨を改正資金決済法で規制する現在のやり方には、主に投資手段として仮想通貨が利用されている現状と隔たりがあるとの指摘があります。そこで日本政府は現在、金融商品取引法(金商法)の枠組みに仮想通貨を移行させる案を審議しています。
金商法への移行が実現すれば、投資家には主に以下のようなメリットが生まれる可能性があります。
税制の改正は長年にわたり個人投資家や仮想通貨業界から実現が望まれてきました。ETFだけ実現させると、仮想通貨の投資マネーが税率が低いETFに流れ、仮想通貨交換業者の取引や収益を減少させることにつながるため、税制改正をETF解禁はセットで実現させるとみられています。
仮想通貨の税率は、日本ブロックチェーン協会(JBA)が2025年7月に政府に提出した資料などを見ると、外国と比べて日本が高い水準にあることがわかります。
以下の表はJBAの資料をもとに作成。個人が1年を超えて保有した仮想通貨の売却益に課される最高税率の比較です。
また、ETFについては規制が整備される前に提供へ向けた動きがみられています。
SBIグループが2024年7月、大手資産運用企業フランクリン・テンプルトンと共同で日本に資産運用企業を設立する計画を発表。現物の仮想通貨を組み入れたETFなどを日本の投資家に提供できるよう法改正されれば、フランクリン・テンプルトンが米国で培った商品組成力や運用力を活かした商品を提供する計画であると説明しています。
他にも、2025年3月には堂島取引所がビットコイン先物の上場認可に向けて申請準備の態勢を整える方針であることが報じられました。先物取引の始まりは、ビットコインETF解禁の重要な布石となる可能性が高いと考えられています。
一方、金商法への移行は投資家保護の強化も実現できますが、必要な開示義務が課されるなど、企業にとっては負担が増えることになります。また、インサイダー規制を課す議論も行われています。
以上が、米国のWeb3制度整備の現状です。米国は世界一の経済大国であり、国家レベルのWeb3制度は長期にわたって国内外から望まれてきました。今後の焦点は、GENIUS法以外の法案の審議です。
前バイデン政権時とWeb3へのアプローチが大きく異なることから、再び民主党への政権交代が起これば規制が再強化されるのではないかとの懸念もありますが、今回の法案は超党派で可決されています。
また、Web3の制度が逆戻りしない根拠として、仮想通貨運用企業Bitwiseの最高投資責任者のマット・ホーガン氏は、民主党への献金を主導してきた米国の金融業界が仮想通貨を支持していること、最大手資産運用会社のブラックロックやJPモルガンらが仮想通貨に投資していることなどから、政治家が方針転換することは想像しがたいと指摘しています。
仮想通貨に肯定的なトランプ政権が誕生し、制度整備が完了して、市場や日本の法整備にどのような影響を与えるのか、非常に注目度が高まっています。
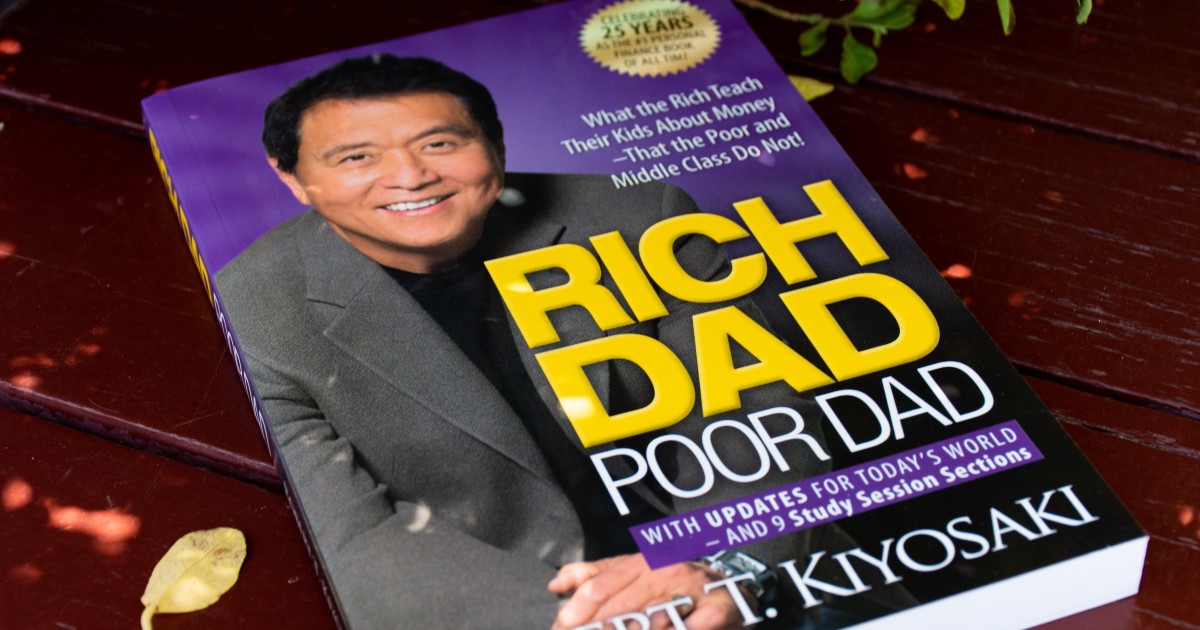
金持ち父さん著者キヨサキ、ビットコインをETFで持つことに注意促す
金持ち父さん著書のロバート・キヨサキ氏が仮想通貨ビットコインETFの注意点を指摘した。現物保有とETFの違いを認識することが大切だと意見している。...

「インターネット金融市場の中枢に」ソラナ創設者が新たな構築計画を発表
仮想通貨ソラナ創設者らが24日、インターネット金融市場ロードマップを発表。アプリケーション制御実行技術ACEで取引順序制御を可能にし、従来型取引所に匹敵する性能実現を目指す。...

シティ、ビットコイン13.5万ドル予測 ETF資金流入が影響
シティグループがビットコイン年末目標価格13万5000ドルを発表。ETF資金流入とネットワーク価値分析に基づく評価モデルで、仮想通貨市場の成長を予測。...

