JPYCの買い方・使い方まとめ|何ができる?今後の活用法・注意点を徹底解説


:contentReference[oaicite:0]{index=0}株式会社は2025年10月27日(月)午後1時、日本初となる日本円建てステーブルコイン「JPYC」と専用プラットフォーム「JPYC EX」を正式リリースした。
JPYCは日本円と1:1で連動し、ブロックチェーン上で即時送金が可能なデジタル通貨だ。銀行を介さずに低コストで資金移動ができ、24時間365日いつでも使える。暗号資産ではなく、資金決済法上の「電子決済手段」として設計されているため、 ライセンスや税務面の負担が軽く、企業導入が進みやすい 。今後は、こうした仕組みを背景に 個人利用シーンの本格拡大 も期待される。
さらに、2025年11月3日時点で、JPYCの総流通量が1億円を超えた(ブロックチェーンデータ探索「 Etherscan 」調べ)。今回はJPYCの使い方を特集形式で解説する。
JPYCは2025年10月27日に正式リリースされた日本初の円建てステーブルコインです。しかし、 今すぐ日常生活で使える場面は限られており 、利用にはWeb3ウォレットやブロックチェーンの基本知識が必要です。ここでは、JPYCを始める前に押さえておきたい3つのポイントを解説します。
JPYCを使うには、 MetaMask(メタマスク) などのWeb3ウォレットが必要だ。これは「デジタルな財布」のようなもので、JPYCを保管・送金するために使用される。
JPYCは現在、 Polygon(ポリゴン)・Avalanche(アバランチ)・Ethereum(イーサリアム) の3つのブロックチェーンで利用可能。ユーザーは購入時にどのチェーン上で受け取るかを選択でき、選んだネットワークによって「対応サービス」や「発行速度」「ガス代(手数料)」が異なる。
ウォレット(例: MetaMask )を利用する際は、 ネットワークを正しく切り替える必要がある 。異なるチェーンを選んだまま送金・受取を行うと、トークンが表示されない・償還できないといったトラブルが起こるため注意が必要。
JPYCは正式リリースされたばかりで、合計発行量は約2,700万円分(初日時点)。既存のサービスでも利用できるが、流動性が低く実質的な利用は限定的。ただし、 対応サービスは急速に拡大中 だ。
発行当日から、JPYCはすでに実際の決済・送金に利用可能だ。JPYCの発行・償還操作は、すべて「JPYC EX」を通じて行われる。マイナンバーカードを使った本人確認後、日本円を入金すれば、デジタルウォレット( メタマスク 等)に即時でJPYCが発行される仕組みだ。
つまりJPYCの「買い方=発行プロセス」「使い方=ウォレット操作」を理解すれば、全体像を掴めるだろう。
登録・発行の流れは、 公式サイト でも画像付きで詳しく説明されている。ここでは仕組みや注意点を中心に整理する。
JPYCの実用化により、個人・法人を問わず多様な決済・送金・運用の選択肢が広がっています。JPYC公式が単独で提供するのではなく、複数企業がAPI連携で独自のサービスを構築する”オープン決済インフラ”として展開されている点も特徴です。
仮に「JPYCレンディング」のDeFiサービスが実現すれば、暗号資産を保有する人にとってゲームチェンジャーになる可能性がある。
どのような仕組みになるのか:
ビットコインやイーサリアム、USDTといった暗号資産を担保として預け入れると、その価値に応じてJPYCを借り入れることができる。担保資産からは金利収入が発生するため、その収益で借入利息を相殺すれば、実質ほぼ無利子での借入が可能になる。借りたJPYCは、JPYC EXで手数料無料で日本円に換金できる。
何が変わるのか:
これまで暗号資産保有者が日本円の生活資金を得ようとすれば、保有する暗号資産を売却(利確)する必要があった。しかしJPYCレンディングが実現すれば、ビットコインやUSDTを担保にJPYCを借りて生活費を賄えるようになる。つまり、暗号資産の値上がり益を享受し続けながら、円建ての生活資金も確保できるという、これまでにない資金管理が可能になる。
実現性は?
サービスの実現性はまだ不透明だが、動きは出始めている。double jump.tokyoとBifrostが、「JPYC」を活用した企業向けDeFiレンディングの推進を発表。
N Suite
による分散管理型ウォレット連携を通じ、法人がJPYCを安全に運用できる仕組みの検証が進む。
BTCFi Boost(利回り提供プラットフォーム)
など関連プロジェクトも含め、商用化を見据えた制度整合型の企業向けWeb3財務基盤づくりが進行している。
JPYC社は今後3年で 発行残高10兆円 を目指している。これは野心的な目標だが、実現すれば日本の金融システムに大きなインパクトを与える規模だ。
円建てステーブルコイン市場は5年後に最大83兆円規模に拡大するとの試算がある。世界全体のステーブルコイン市場は既に時価総額42兆円超、1日取引高40兆円規模に達しているが、その98%以上が米ドル建てだ。日本が制度整備を先行したことで、円建てステーブルコインが新たな市場を切り開く可能性がある。
日本は2022年の資金決済法改正で、世界に先駆けてステーブルコインの法整備を完了した。JPYCは国内初の資金移動業者として円建てステーブルコインを発行する事業者となり、大手銀行ではなくスタートアップが第一号の認可を得たことは注目に値する。この規制枠組みが国際標準になれば、東京がステーブルコインのハブとなる可能性もある。
今後の展開
JPYC社は現在、USDCとの交換・販売を可能にする「電子決済手段等取引業」のライセンス取得を進めている。また、トークン証券(STO)や企業トークン発行への参入も視野に入れており、Circle社(USDC発行体)のIPOに倣ってJPYC自身もIPOを目指している。監査法人を導入して体制を整備中で、スタートアップから上場企業への道筋を描いている。
資金決済法の改正により、発行額の50%を上限として国債や定期預金で運用できるようになった。この金利収入をビジネスモデルの柱とすることで、ユーザーへの手数料を無料にできる。米Circle社と同じ収益構造だ。
関連: ステーブルコインの種類一覧|市場規模・取引量・規制の行方
日本円建てステーブルコイン「JPYC」は価格が安定しているため、一見すると課税や価格変動リスクが少ないように思われる。しかし、 利用方法によっては課税対象となるケースがある 。たとえば、JPYCでNFTや他の暗号資産を購入し、それを売却して利益が出た場合、その差益は「雑所得」として課税される。また、DeFiサービスに預けて利息や報酬を得た場合、受け取った時点で経済的利益とみなされ、年度ごとの申告が必要になる。
さらに、ステーブルコイン利用によるキャッシュバックや特典も、一時所得として課税される場合がある。副業や投資と合算される総合課税となるため、 年間利益が20万円を超える場合は確定申告 を行う必要がある。法人利用では、事業会計上の損益計上・帳簿管理が求められる点にも注意したい。
レンディング(仮想通貨担保ローン)のように、BTCやETHを担保にJPYCを借り入れる行為自体は、原則として課税されない。担保資産は返済後に戻るため「売却」には該当しないからだ。ただし、担保資産から得られる利息や報酬は課税対象となるため、年度ごとの損益計算が重要になる。
税務面に加えて、 セキュリティリスク にも十分な注意が必要だ。秘密鍵の漏洩や紛失、フィッシング詐欺は自己管理型ウォレットで特に起こりやすい。対策としては、ハードウェアウォレットなどオフラインでの鍵保管、リカバリーフレーズの紙保管、公式サイトをブックマークして偽サイトを避けるといった基本を徹底したい。
また、取引履歴は必ずCSVやスクリーンショットで保管し、年度末時点での円換算を行うことで税務リスクを最小化できる。制度や課税ルールは今後も変化が見込まれるため、公式発表やガイドラインの更新を随時チェックしよう。
関連記事: ステーブルコインの税金ルールと管理の基本|CoinPost解説
関連: 2025年夏、日本円ステーブルコインの新たな幕開けJPYC岡部典孝氏のビジョンとは|独占インタビュー | ステーブルコインの税金ルールと管理の基本|CoinPost解説

欧州が仮想通貨・証券の統一監督機関設立を検討 米SECモデルに
欧州委員会が仮想通貨・証券取引所を一元監督する機関を構想している。米証券取引委員会をモデルにしており、ESMAの権限拡大案も検討していると伝えられる。...
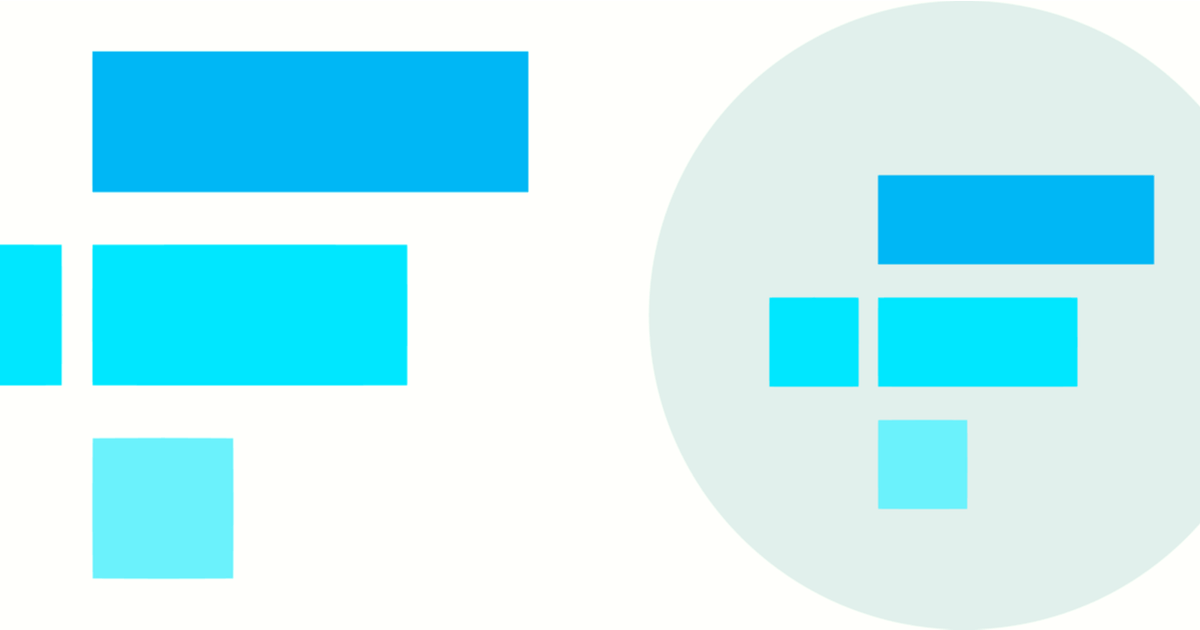
FTX債権者は仮想通貨上昇分の恩恵受けられずか 債権実質回収率の試算は9%~46%
仮想通貨取引所FTXの債権者は破綻時の現金相当額で弁済されるため、債権者はビットコインなどの上昇分を受け取れないことになる。債権者代表は、実質回収率は9~46%と推算した。...
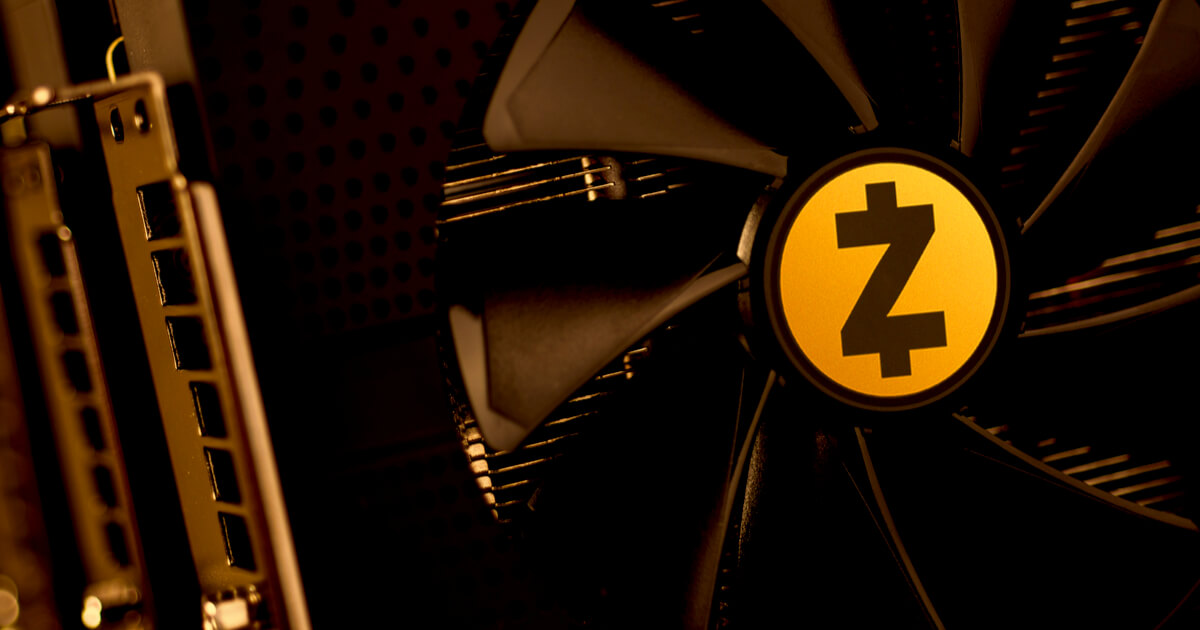
仮想通貨Zcash、プライバシー取引機能をさらに強化へ 新ロードマップ公開
匿名機能を重視する仮想通貨Zcashが2025年10~12月期のロードマップを発表した。プライバシー機能を大幅強化し、スワップ毎の使い捨てアドレスなどを導入する計画だ。...

